2025年(令和7年)2月18日、厚生労働省は「あん摩・マッサージ・指圧業、はり業、きゅう業、柔道整復業」に関する新たな広告ガイドラインを発表しました。
この指針の目的は、利用者が正確な情報を得て適切な施術を受けられるようにすることであり、
施術所の広告規制を強化し、誤解を招く表現を排除することを主眼としています。
新しい広告ガイドラインの概要、
具体的な規制内容、
そして施術所や広告担当者が気をつけるべきポイントについて、
詳細に解説していきます。
1. あはき・柔整広告ガイドラインの背景と目的

1-1. 広告規制の必要性
あはき・柔整の施術所は、日本全国に数多く存在し、利用者の健康を支える重要な役割を果たしています。
しかし、近年、以下のような問題が指摘されていました。
-
施術効果を誇張する広告の増加
- 「短期間で改善!」
- 「この施術で必ず治る!」
-
医療機関と誤認させる表現
- 「○○クリニック」「○○診療所」といった名称の使用
- 「医師監修」などの不適切な表記
-
無資格者による違法な施術広告
- 資格を持たない者が「整体師」「カイロプラクター」などを名乗り、医療行為に近い施術を宣伝
これらの広告が氾濫することで、利用者が誤った情報をもとに施術所を選んでしまい、健康被害や経済的損失を被るケースが増加していました。
そこで厚生労働省は、あはき・柔整業界の広告基準を明確化し、適正な広告を促進することを目的として、新しいガイドラインを策定しました。
1-2. ガイドラインの適用範囲と影響
この広告規制は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師が運営する施術所や、これらの施術所を宣伝する広告に適用されます。
2. 新しい広告規制の概要

2-1. 広告とみなされる要件
新しいガイドラインでは、以下の3つの要件を満たす情報は「広告」とみなされ、規制対象となります。
- 誘引性:施術所に利用者を誘導する意図がある
- 特定性:施術者や施術所の名称・住所などが明示されている
- 認知性:一般の人が目にすることができる
2-2. 広告可能な内容
広告で掲載可能な情報は、以下の項目に限定されます。
- 施術者の氏名・住所(「国家資格保有」の記載は可能)
- 施術所の名称・電話番号・所在地(ただし、医療機関と誤認される表現は禁止)
- 施術日・施術時間(「診療日」「初診・再診」など医療用語の使用は禁止)
- 予約制の有無、出張施術の実施
上記以外の情報を広告に含めることは禁止されており、違反すると行政指導や罰則が適用される可能性があります。
3. インターネット広告の規制強化

3-1. インターネット広告の重要性
近年、あはき・柔整業界でもウェブサイトやSNSを活用した広告が主流になっています。
今回のガイドラインでは、こうしたインターネット広告についても明確な基準を設定し、虚偽や誇大な広告が拡散するのを防ぐ狙いがあります。
3-2. インターネット上の広告として規制対象となるもの
次のようなものは「広告」とみなされ、規制の対象になります。
- 検索エンジンのリスティング広告(Google広告、Yahoo!広告など)
- バナー広告(他のウェブサイトやブログに掲載される広告)
- SNSの公式アカウントの投稿(Instagram、Twitter、Facebook、TikTokなど)
- YouTubeの動画広告
- 口コミサイトでの施術所紹介(特に、施術所が掲載料を支払っている場合)
3-3. インターネット広告で禁止される表現
特に、以下のような表現はインターネット広告で禁止されています。
① 施術の効果を保証する表現
× 「肩こりが必ず治る!」
× 「この施術で改善します!」
② 競合との比較広告
× 「当院は他院より圧倒的に効果が高い!」
× 「○○治療院より料金が安い!」
③ 煽るような表現
× 「この施術を受けないと体調が悪化する!」
× 「今だけ特別価格!早い者勝ち!」
④ 医療機関と誤解させる表現
× 「○○クリニック」「○○診療所」「○○科」
× 「医師推奨の施術」
違反すると行政指導の対象となるほか、悪質な場合は罰則が科される可能性があります。
4. 違反した場合の罰則と指導方法

4-1. 行政指導の流れ
新しい広告ガイドラインに違反した場合、厚生労働省や都道府県の行政機関が指導を行うことになります。違反が発覚した場合の対応の流れは以下の通りです。
-
指導・警告(初回)
- 「広告内容を見直すように」という行政からの指導が入る。
- 指摘を受けた施術所は、広告を修正する必要がある。
-
業務改善命令(再三の違反)
- 初回の指導に従わず、繰り返し違反が見られる場合は、業務改善命令が出される。
- これに従わない場合、罰則の対象となる可能性がある。
-
罰則の適用・施術所の公表(悪質な違反)
- 特に悪質な違反を行った施術所は、施術所名が公表されることがある。
- さらに、行政処分(営業停止・罰金)などの法的措置が取られる可能性もある。
4-2. 施術所がリスクを回避するための対策
施術所が広告規制違反を防ぐためには、以下のような対策が必要です。
-
広告のチェックリストを作成する
- 広告を作成する際に、ガイドラインに適合しているかをチェックするリストを作成し、適用する。
- 施術の効果を誇張しないか、過度な煽り表現がないかを確認する。
-
広告代理店やマーケティング担当者と連携する
- 広告代理店を利用している場合は、施術所側も規制を理解し、適正な広告運用を行う。
-
最新の法令やガイドラインの情報を定期的に確認する
- 今後も規制が強化される可能性があるため、定期的に厚生労働省や都道府県の公式情報をチェックする。
5. 今後の影響と施術所が取るべき対応

5-1. 施術所への影響
今回のガイドライン改正は、特にインターネット広告を利用している施術所に大きな影響を与えることが予想されます。
従来は、あはき・柔整業界において広告の規制はあったものの、SNSやウェブサイトでの宣伝に関しては明確なルールがなく、各施術所が独自の広告戦略を取ることができました。
5-2. 施術所が注意すべきポイント
今後、施術所は広告を作成する際に、以下の点に特に注意する必要があります。
① 施術の効果を誇張しない
施術の具体的な効果を明記することは可能ですが、「○○が必ず治る」「絶対に痛みがなくなる」といった保証表現は禁止されます。
広告を作成する際は、「○○の改善をサポート」「○○にアプローチ」といった、あくまで施術の役割を強調する表現にすることが望ましいでしょう。
② 医療機関と誤認される表現を避ける
「○○クリニック」「○○診療所」といった医療機関を連想させる名称の使用は厳禁です。
加えて、「治療」「診断」といった医療行為を示唆する表現も控える必要があります。
③ SNSや口コミサイトでの表現にも注意する
例えば、以下のような投稿は問題になる可能性があります。
- 「○○さん(著名人)も通っている施術所です!」(有名人を利用した宣伝)
- 「この施術を受ければ、○○が劇的に改善!」(効果の保証)
- 「今なら特別価格!早い者勝ち!」(過度な煽り表現)
これらの表現を使用すると、ガイドライン違反とみなされ、行政指導の対象になる可能性があるため、慎重に対応する必要があります。
6. インターネット広告の具体的な運用方法

6-1. 広告作成時のポイント
ガイドラインに準拠しながら、効果的に施術所を宣伝するためには、以下のようなポイントを押さえる必要があります。
① 利用者が知りたい情報を正確に伝える
誇大広告が禁止される一方で、施術所の基本情報や提供するサービスの内容を正確に伝えることは推奨されています。例えば、以下のような情報は適切に記載できます。
- 施術の種類(例:「国家資格を持つ施術者が提供する○○施術」)
- 施術の流れ(例:「初回カウンセリング→施術→アフターケア」)
- 料金体系(例:「○○円(税込)」)
② 口コミやレビューの扱いに注意する
口コミサイトやGoogleマップのレビューは、施術所が直接関与していない限り広告には該当しません。
例えば、以下のような行為は違反とみなされる可能性があります。
- 施術所が自ら良い口コミを投稿する
- 悪い口コミを削除するよう利用者に依頼する
- 「この口コミを見た人は割引!」といったキャンペーンを実施する
7. ケアマネ営業はガイドライン違反になるのか?

7-1. ケアマネ営業と広告規制の関係
ケアマネージャーに対する営業活動が「広告」とみなされるかどうかがポイントになります。
広告とみなされる要件(ガイドラインより)
広告と認定されるには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 誘引性:施術所に利用者を誘導する意図がある
- 特定性:施術者や施術所の名称・住所などが明示されている
- 認知性:一般の人が目にすることができる
この要件を満たす場合、ケアマネージャー向けの営業活動でも「広告」とみなされる可能性があります。
7-2. 具体的な営業手法ごとの違反リスク
ケアマネージャーへの営業活動がガイドライン違反にあたるかどうかは、営業の方法や表現によります。以下に具体例を挙げて解説します。
① 直接訪問や電話営業(個別相談) → 違反の可能性は低い
- 対象:ケアマネージャーとの1対1の面談や、施設訪問での営業
- 内容:施術所のサービス説明、料金案内、利用者の送客依頼
- ガイドライン適用の可能性:
- 一般の人が目にしないため、「認知性」の要件を満たさない。
- そのため、原則として広告には該当しないと考えられる。
▶ 注意点:
- 「〇〇の症状が必ず改善します」といった誇大表現はNG。
- パンフレットやチラシの配布は可能だが、ガイドラインに適合しているか確認が必要。
② ケアマネ向けの勉強会・セミナー開催 → 内容によっては違反の可能性あり
- 対象:ケアマネージャー向けに施術に関する勉強会や説明会を開催
- 内容:施術方法の紹介、実績の説明、特定の症状への効果の強調
- ガイドライン適用の可能性:
- 勉強会自体は広告ではないが、配布資料や発表内容が広告とみなされる場合がある。
- 例えば「当院の施術で〇〇の症状が治る」といった表現は誇大広告に該当する可能性がある。
▶ 注意点:
- 施術の効果を保証しない表現にする。
- ガイドラインに準拠したチラシやパンフレットを配布する。
③ ケアマネ向けのDM・パンフレット送付 → 内容によっては広告規制の対象
- 対象:郵送やメール、FAXでの営業活動
- 内容:施術の特徴や実績の説明、利用者紹介の依頼
- ガイドライン適用の可能性:
- DMやパンフレット送付は施術所の情報を掲載し、誘引性があるため広告とみなされる可能性が高い。
- 広告可能な範囲(施術所名、施術者名、連絡先など)に限定すれば問題なし。
- 施術効果の保証や「特別キャンペーン」などの表現はNG。
▶ 注意点:
- 「改善率〇〇%」「〇〇病が治る」といった表現は避ける。
- 「〇〇の専門院」といった表現も、特定の効果を暗示するため注意が必要。
④ 施設のホームページやSNSでケアマネ向けの宣伝 → 違反の可能性が高い
- 対象:施術所のウェブサイトやSNSで「ケアマネ向け情報」として施術をPR
- ガイドライン適用の可能性:
- ウェブサイトやSNSは一般の人も閲覧可能であり、「認知性」の要件を満たすため、広告とみなされる可能性が高い。
- そのため、広告規制に従う必要がある。
▶ 注意点:
- 施術の効果を強調しすぎない(「〇〇の症状に効く」などは避ける)
- 割引や特典を強調しない(「今なら初回無料!」などはNG)
- エビデンスのない情報を掲載しない
8. 介護施設でのマッサージ体験会はガイドライン違反になるのか?

8-1. マッサージ体験会の広告規制適用のポイント
介護施設でマッサージ体験会を実施する場合、それが「広告」とみなされるかどうかが問題になります。
以下のようなケースでは、体験会が広告と見なされる可能性が高いです。
① 一般利用者向けに広く募集する場合 → 違反の可能性あり
- 施設のホームページやチラシで広く宣伝する
- 「この施術で症状が改善!」といった表現を含む
▶ 違反となる可能性が高い
- 誘引性・特定性・認知性の要件を満たし、広告とみなされる可能性が高い。
② 施設利用者のみを対象にする場合 → 違反の可能性は低い
- 施設内で利用者限定の体験会を実施し、一般に告知しない
- 施術の効果を誇張しない
▶ 広告とみなされない可能性が高い
- 「認知性」を満たさないため、広告には該当しない可能性がある。
総括・まとめ

広告の定義として、
- 誘引性:施術所に利用者を誘導する意図がある
- 特定性:施術者や施術所の名称・住所などが明示されている
- 認知性:一般の人が目にすることができる
上記3要件を満たすものが「広告」として定義されます。
この要件を満たす場合、紙媒体広告(チラシ、ポスター、看板など)はもちろん、SNS投稿や口コミサイトの情報も広告とみなされる可能性があります。
さらに、広告で掲載可能な内容は施術所の基本情報や施術時間などに限定され、施術の効果を保証する表現や、競合との比較、過度な煽り表現などは禁止されました。
今まではネット上の情報については言及されていなかったため、各治療院においてさまざまな広告やSNS戦略がとられていました。
しかし今後はオンライン上の情報も含めて慎重に情報を発信していく必要があります。
社会保障審議会にて詳しい検討がなされますが今後の情報に注目が集まります。
【お悩み相談・各種情報発信はこちら】
【オープンチャット】
「新・訪問鍼灸マッサージ総合情報局(訪問マッサージ 開業 まとめ)」
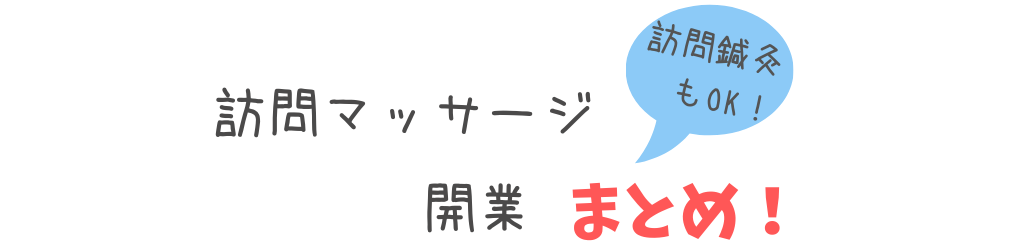





ご質問・ご感想